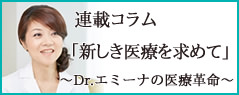連載 「新しき医療を求めて」
連載 第二回 「薬いらずの我が家」・「医師を目指して」
薬いらずの我が家
私は風邪をひくと高熱が出て扁桃腺がひどくはれることが多かったが、病院や薬のお世話になったことは一度もなかった。母は私をふとんに寝せて、葛湯やおかゆを食べさせ、どんどん汗を出して、下着をとりかえる、そうするうちに一晩で熱は下がり治った。
ある年の春は、アレルギー性鼻炎になりいち早く症状を察知した母は、即座にかかりつけの鍼灸医のところへ連れて行ってくれ、鼻の脇に何本か針を打ってもらって一度ですっきり治ったこともあった。また食あたりで下痢になったときも、お手製の梅酢を水で薄めたものを飲むと、悪いものがすっかり出て治りが速かった。
妹は小児喘息であったが、これもその鍼灸医のところで治ってしまった。最近は特に、子供が少しでも熱を出すとあわてて病院を受診し、解熱剤や抗生物質を求める方が多く見受けられるが、私は薬を飲ませず自然治癒に導いてくれた母に感謝している。
そして、現在の私の医療に対する姿勢の基礎は、こうした母の行動、考え方によって培われたように思う。
医師を目指して
私が千葉高校3年の9月、突然母が入院した。診断は子宮筋腫で、かなり大きくなっており、このまま帰宅したらいつ大量出血するかわからないと医師に告げられての入院であった。入院に至るまでの何年かの間、母は慢性的な貧血のため顔は青白く、疲労や食欲不振、不正出血に加え、しまいには腹部を手で押さえなければ尿が出ないなどの症状も出現した。大きくなりすぎた筋腫が膀胱と尿道を圧迫していたのである。何の知識もない私はそういう母を目前に見ていても、働きすぎで疲れているのかな、と心配するくらいしかできなかった。
今振り返ると、このことをきっかけに私は医師になろうと決意したように思う。知識と経験さえあれば、こんなにひどくなるまで放っておくことはしなかっただろうと、自分の無力さをもどかしく感じた。
入院当初、赤血球の量が正常の3分の1しかなかったため、それが回復するまで治療してから手術が行われ、術後経過は良好だった。
ところが、2週間たっても退院の話が全く出ないのである。いくら知識がなくとも、私はおかしいと思いはじめていた。父は、私たち娘二人には本当のことを隠していたが、ある朝、食事中に父がめがねをはずし涙ぐみながら洗面所へかけこむ姿を見て、「あ、お母さん、悪いんだな」と直感した。
案の定、手術で摘出した筋腫が病理検査の結果、悪性ということがわかったというのである。母は個室に移され、抗がん剤治療を受けた。
この間、私は医学部への進学を決め、志望校もしぼって受験勉強を始めていたが、母が悪性の診断を受けてから、私の足は病院に向かうことができなくなっていた。
抗がん剤の副作用で、髪の毛が抜け、やせ細っている、そんな母に会える勇気がなかった。会ってしまえば自分の決意が揺らいで、その場で泣き崩れてしまうのではないか、と怖かったのである。そして、この春に何がなんでも医学部に合格する姿を母に見せるしかない、もし失敗したら次の春はもう母はこの世にいないかもしれない、という思いだけが私を駆り立てていた。
また我が家では母が入院する数ヶ月前から、九州で暮らしていた母方の祖母と身障者の伯父を引き取り同居、母が身の周りの世話をしていた。
母のいない間、長女である私が先頭に立ち、食事作りは私の担当、その他の家事は妹と分担したものである。朝はお味噌汁とごはんに納豆、青菜にぬか漬けを用意し自分たちのお弁当を作って学校へ出かけ、夕方学校の帰りに食材の買い物をした。帰ってみると、ひっそりとした居間で祖母と伯父が二人、心細そうに座っていたものである。
できあいの物を買えば早くてよかったのかもしれないが、我が家にはそういう習慣が全くなかった。私の料理の腕は、この頃に養われたのかもしれない。
片付けを終えた夜の9時過ぎからようやく受験勉強ができるという状況だった。それでも、当時そのような生活を大変だとか苦痛には思わなかった。
このような日々が3ヶ月目に入った頃の夜、父が
「お母さんがあさって帰ってくるよ」と言うではないか。
「えっ、ほんとう?うそでしょう。」
「いや、ほんとうだよ。」
この時、私は母が医師に見放されたのだと思った。実際、この直感はある意味であたっていたことが数年後にわかったのだが、当時はあまりにも喜ぶ父の顔に、私も母の状態がよくなったのだと思うようになっていった。
退院後、母は少しもじっとしていなかった。今まで皆に迷惑をかけてごめんね、と休む間もなく家事をこなし、祖母の世話をしていた。台所に立っている後ろ姿が、以前よりも小さくなり、ベッドに寝たきりだったせいで、ひざから下がまるで干した大根のように張りがなくなっていたのが今でも脳裏にやきついている。そして手術に心労と、心身へのストレスのせいで何歳か年をとってしまったようにも見えた。
退院後、かなりたってから母が私に話してくれたことがある。
「悪性とわかり個室に移ったとたん、先生も看護婦さんも病室に来る回数が減ったのよ。先生は見えない日もあってね。看護婦さんも、子宮筋腫の診断のころは、よく会いにきてくれて冗談言ったりしていたのに、急によそよそしくなって必要な処置が済んだら話もせずに部屋を出て行ったりして。だから、あなたがお医者さんになったら、どんな患者さんの所にも顔を出して話しをしてあげてね。むしろ状態が悪い人の所ほど、ね。」
母は、どんなに孤独だったであろうか。悪性と告げられ、いつまで命があるか、残された家族はどうなるだろう、などと不安と恐怖の中にいただけでなく、医師や看護婦との対話も許されず、逃げるように病室から去っていく姿をみてどんな気持ちであっただろう。無言のうちに、「あなたは死へ向かっている」と宣告され、全て見放されたような気持ちだったのではないだろうか。
本来、医療従事者は患者様が治癒するために、精神面・肉体面双方に対してケアを行うべきであるにもかかわらず、母は心身ともに打ちのめされているところへ、さらに上からくさびを打ち込まれたようなものである
「最初の頃は抗がん剤の治療を受けながら、毎晩ベッドで布団をかぶって声を殺して泣いていたのよ。でもね、おばあちゃんとおじさんをあの世に見送るまでは、私は死ぬ訳にはいかない、受験前の娘にこれ以上負担をかけることもできない、神様、どうか私に命を下さい!と一心に祈り続けたよ。」と。
この母の気力と強い信念がなかったら、どうなっていたかわからない。事実、それから数年後、母と同時期に入院していた女性が当時の主治医に会い、母が元気にしていると話したところ、「まだお元気なのですか」と非常に驚いていたという。もうとっくにこの世にいないと思っていたのである。
母は、今年で術後16年目になるが、とても元気にしてくれている。