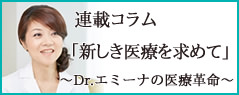連載 「新しき医療を求めて」
連載 第四回 「研修医」
研修医
1996年4月、私は母校の第二内科(内分泌内科)へ入局した。ここは、内分泌(ホルモン)の病気を専門とし、その他の内科疾患も広く診療する一般内科も行っていた。最初の2年間は院内の各科を3ヶ月ずつ回り、入院患者を受け持つ、研修医の期間である。
大学からの給与が4万5千円で、外病院での勤務も許されていないため、医師になってもなお親からの仕送りに頼る生活であった。
入局早々、ある先輩医師から「まだまだ君たちは使い物にならないのだから、勉強させてもらっていると思って丁度いいのですよ」と釘をさされ、ああ、そういうものなのだと納得し、新しいことを覚え、身につけることに一生懸命の毎日であった。
学生時代に学んだことも役にたったが、やはり医師になると責任も要求されることも学生とは比べ物にならなかった。
初めて白衣をまとい、聴診器を首から下げて受け持ちの患者さんの部屋へ行く時の緊張感は今でも忘れられない。自分よりも人生の先輩である人が皆、自分のことを「先生」と呼ぶのである。
その違和感が無くなるまでしばらくかかったが、なぜかそう呼ばれることで、とんでもない世界に放り出されたような気さえしていた。
入局後、教授回診で初めて受け持ち患者さんのプレゼンテーションをした時の緊張感も鮮明に覚えている。
データも全て覚えて、カルテも見ずに行うことが伝統、と上司に言われ前の日から何度も予行演習をして臨んだが、当日は病院に行く前から心臓がドキドキしていた。
教授を筆頭に、助教授、講師その他医局員がずらりと並ぶ前で、無事に報告を終えたあとの開放感は格別だったが、こんな緊張感がこれからずっと続くのかしらと、不安に思ったものである。
とにかく無我夢中に働き、馬車馬と呼ばれたこともあった。知識や経験が未熟なのだから、まずはフットワークよく動くこと、と思っていた。また、そうやって身軽に動いていると上の先生も、色々と教えてくれたりもした。
わからないことがあれば、専門の先生のところへ行って意見を求めた。医師になった時母が、「労力をおしんではいけないよ。」と忠告してくれたことがよかったのだと思う。
夜間の救急当直で、真夜中の地下にある部屋にカルテを取りに行くのも研修医の仕事であった。さすがの私もこればかりは苦手で、ついつい足取りが重くなった。
一人で地下の薄暗い廊下を歩き、霊安室の近くの真っ暗な部屋へ入り急いでカルテを見つける、帰るときは足早に走ったものである。
気付いたら夜明けということもしばしばで、当直明けの日も終日とおしで働く。よく医療事故をおこさなかったと冷や汗が出る思いがする。
今でこそ医療の質を高めるために研修医の労働条件が問題になり改善されつつあるが、当時の研修医は3Kといって「きつい・きたない・苦しい」が当たり前という世界であった。
医師は終生、患者様から学ぶという要素が非常に多いと私は思っているが、この研修医の期間は特に、知識だけでなく、注射や処置などの技能、医師としての態度も含めて患者様に育てて頂いた部分がとても大きく、ただただ感謝するばかりである。
もちろん、先輩医師から教わったことは数知れない。
呼吸器内科で、80歳代の男性(Sさん)を受け持ったときのことである。その方は肺炎のため緊急入院し、すぐに治療を開始したが状態は悪化する一方であった。
入院後5日目の夜、Sさんの状態はさらに悪化し、肺だけでなく腎臓や肝臓、その他全身に障害がでて、いわゆる多臓器不全の状態に陥り薬剤を投与したが全く反応はなかった。
呼吸状態も人工呼吸器をつけなければ空気を吸い込むことさえ困難な状況であった。当然、病棟の他の医師たちの誰もが、いよいよ人工呼吸器を装着するものだと思っていた。
私は、指導医のI先生とともにSさんのご家族と話し合った。ご家族は、Sさんが苦しまないようにしてほしいということが何よりの希望であった。
I先生と私は、今までの経過から、人工呼吸器を導入しても回復の見込みは難しく、かえってSさんの負担、ご家族の心身の負担を招くことになると判断し、現状の治療内容のまま状況を見守ることにした。Sさんが苦しまないように、という家族と我々の気持ちが一つになったのである。
私たちのこの判断に対して、他の研修医や一部の呼吸器内科医は非難をした。
「あの二人は、Sさんを殺すつもりだ。何を考えているのか。」と。
私は、医師になって初めて、このような状況を体験し、体を動かしながらも心がついてこない、そして悲しいとか苦しいとかそういう感情には分類しきれないものを感じていた。
数日前まで私と話をしていた人が、今瀕死の状態にいる、有効とされている強い薬剤も効かない、自分が学んできた医療の知識が全く効を奏しない、医療の限界、等々。
そして、延命治療を行わないことを、まるで非国民のように非難し冷たい態度をとる医師たちに対する空しさ、怒り。
私は、悩んだ。夜が長く、長く、朝がこないかもしれないほど長く感じた。
だが、いよいよSさんが最期のときを迎えた。病室で家族が見守るなか、息をひきとられた。
私は手が震えそうになるのを必死に抑え、Sさんの瞳孔反射がないこと、心臓の音が止まっていることを確かめ、Sさんが亡くなられたことをご家族に告げた後、どうしたらいいのかわからず、ただ立って下をむいていることしかできなかった。すると、横にいたI先生が、
「Sさん、よくがんばられたと思いますよ。皆さんに良くして頂いて大往生でいらっしゃったと思いますよ。」といった途端、皆こらえていたものがこみ上げるかのように、部屋中に嗚咽が響き渡った。
そのI先生の言葉に、私も涙がこみ上げてきて、それまで抑えていた何かが解放されたように感じた。
医員室へ戻り、呆然としている私にI先生が、
「人は、病気で死ぬんじゃない、寿命で死ぬんだよ。家族はね、もっとああしてあげればよかった、と悔やんでも悔やみきれない、救われない気持ちでいるんだよ。だからそれを、本人が喜んでいたと言ってあげることで家族は自分たちの心を保つことができるんだ。実際、本人もそう思っていると思うんだよ、僕は。」
その後しばらくして、Sさんのご家族から手紙が届いた。
あの当時のI先生と私の判断、対応に対しての御礼と、自分たちも心底、Sさんが満足してくれたと思えるようになったとの旨がしたためられていた。
初めて受け持ちの患者様が亡くなったこの時の体験が、その後の臨床医としての私のあり方に大きな影響を与えてくれたように思う。